出産や病気による入院、高額な治療をすることで皆さんのお金が飛んでいきますよね・・・
みなさんが知ることで絶対に損はしない
高額療養費制度(こうがくりょうようひ)
高額療養費について どこまで知っていますか?
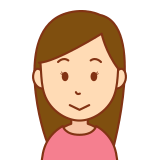
高額療養費って言葉はなんとなく聞いたことがあるよ・・・
でも制度まではあまり知らないかな💦
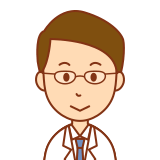
高額療養費にはいくつかあって
・高額な医療費の支払いを一定金額で止める
・医療費の払い戻し の2通りあるよ!
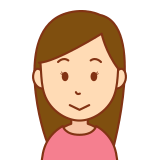
もっと具体的に知りたい!
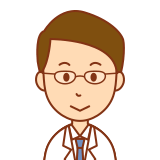
これから解説していくので、一緒に勉強しよう!
適切な医療保険はお金の専門家から学ぼう!
\ 今ならもれなくミスタードーナツのギフトチケットがもらえる! /
健康保険 医療費の限度額について
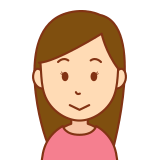
医療費の限度額って何なの?
こう思われる方は多いと思います。
そもそも皆さん(国民)は、何かしらの公的健康保険に加入しています。
これが国民皆保険という制度です。
- 会社員であれば社会保険
- 公務員や教員の方は共済組合
- 自営業者やフリーランスの方は国民健康保険(国保)
- 建設・医師の方は建設国保や医師国保など…
加入している公的保険には、所得によって医療費の支払い限度額があります。
社会保険と国民健康保険 医療費の限度額
ここでは協会けんぽ(全国健康保険協会)を例にします。
その他の方は加入している保険のHPをご確認ください。 ※協会けんぽ(全国健康保険協会)HPから抜粋
※協会けんぽ(全国健康保険協会)HPから抜粋
 ※東京都新宿区HP から抜粋
※東京都新宿区HP から抜粋
これらのように所得によって医療費の限度額が変わります。
医療費の限度額で何がわかるのか
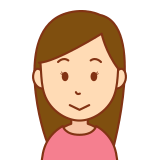
医療費の限度額があることが分かったけど、どのように活かされるの?
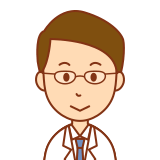
医療費の限度額を知ることで
- あなたは、医療機関で57,600円(例)以上、自己負担をする必要がない
- 医療機関で57,600円(例)以上、自己負担をしたら払い戻しされる
ということがわかるよ! ※金額(57,600円)はあくまで例です。
申請方法の解説
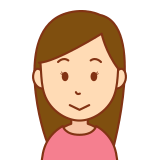
具体的にどのように申請していくの?
これから申請方法を解説します!
申請といっても「診療(入院)前」と「診療(入院)後」の2通りあります。
(1)診療(入院)前」のケース
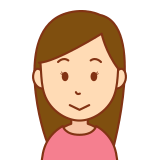
入院するんだけど、「高額療養費の限度額認定証を申請」するよう病院から言われたよ。
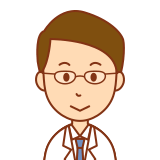
「限度額認定証」とは、医療費の支払いを事前に限度額までストップしてくれる証明書のことだよ。申請方法はこれから解説するね!
ちなみに病院から言われなくても自分から申請しても良いんだよ。
申請方法
協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している場合
- 全国健康保険協会HPから申請書を印刷
- 保険証(もしくは資格証明書)も確認しながら申請書を記入
- 記入済み申請書を郵送
・約1週間で「限度額適用認定証」が郵送されます。
・「○○株式会社健康保険組合」など大手企業や団体は個々に組合が組織されている場合がありますので、加入の健康保険組合から申請書を印刷してください。
・会社から申請書の郵送などをお願いできることもあります。
※マイナンバーカードと保険証を紐づけている場合は、限度額認定証の発行が不要になる場合があります。
- 住所地(住民票を置いている市区町村)の役場(国保担当課)に行く
持参物:本人の保険証(代理申請が可能な場合が多いです) - 限度額認定証が必要と伝える
- 申請書を記入
基本的には即日発行されます。
ただし、保険料(税)の滞納があると、発行できない・制限がつくことも。
- 医師国保、建設国保なども上記とほとんど変わりません。
- 加入の健康保険のHPなどを確認してください。
- 発行されたら医療機関の窓口に提出しましょう!
(2)診療(入院)後」のケース
(1)の申請を忘れて医療費を支払ってしまった!という方
医療費の限度額以上に病院で支払った場合は、差額分が還付されます。
協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している場合
- 医療機関の窓口で、医療費を支払う
医療機関で受け取る「領収書」は捨てない! - HPから「健康保険高額療養費支給申請書」を印刷し記入
- 記入済みの申請書を郵送
・レセプト(診療報酬明細書)が医療機関→健康保険に届いてから差額分が支給されるため、支給まで2〜3ヶ月程度かかります。
- 医療機関の窓口で、医療費を支払う
医療機関で「受け取る領収書」は捨てない! - 住所地(住民票を置いている市区町村)の役場(国保担当課)に行く
持参物:世帯主の通帳、世帯主の印鑑、医療機関の領収書 - 窓口で「高額療養費の払い戻し手続き」の旨を伝え、申請書を記入
・レセプト(診療報酬明細書)が医療機関→各市区町村の国民健康保険に届いてから差額分が支給されるため、支給まで2〜3ヶ月程度かかります。
・市区町村によっては、世帯主あてで「高額療養費の払い戻しのお知らせ」が届くこともあります。
⚠️詐欺と間違わないようにご注意ください。
不安に思った場合は、市区町村役場に直接電話をして確認することが重要です✅
限度額の計算方法や注意点
限度額適用区分は、所得や標準報酬月額を基に計算されますが、
ここでは、領収書などを確認しながら計算する場合の方法を紹介します。
保険適用される医療費のみを計算対象とする!
これができれば限度額(医療費の払い戻し)の計算ができる!
保険適用の医療費のみを計算対象としますので、下記のような保険適用外診療は対象になりません。
- 自由診療(インプラント、レーシックや美容整形)
- 予防接種(インフルエンザやHPVワクチンなど)
- 健康診断(人間ドック、特定健診や通常の健康診断)
- 入院時の設備やサービス(個室、テレビ/冷蔵庫などの利用料など)
- その他の保険適用外診療
領収書に「保険診療」と記載されている金額は保険適用されている医療費です。
「保険外」や「保険適用外」と記載されていれば保険適用外です。
月を跨(また)いでしまうと再計算
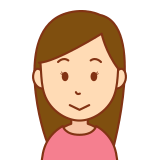
月を跨(また)ぐと再計算ってどういうこと?
例)1月20日〜2月10日まで入院した場合
- 1月20日〜1月31日分
- 2月1日〜2月10日分 の2つで計算する必要があります。
医療費の限度額が計算されるのではなく、その月毎で計算されます。
入院総額(保険適用分)では限度額を超えるが
月ごとに計算すると限度額が超えないので払い戻しはなくなる
もし入院をする場合は、できる限り1月(ひとつき)にまとめたいですね。
入院・外来・歯科はそれぞれ別々で計算する
70歳未満の方が対象の内容
ここ意外と知らない人が多いのですが、
単純に医療費を支払って合算すれば良いというものではなくて、
入院・外来・歯科はそれぞれ別々で計算しなければなりません。
ただし、医療機関から処方された調剤薬局は紐づけることができます。
例)太郎さん(30歳・独身)
区分「エ」[自己負担限度額57,600円]
・A病院(外来) 20,000円
・B薬局(調剤) 5,000円[A病院からの処方]
・C歯科(歯科) 6,000円
・D病院(入院) 30,000円
支払総額 61,000円
自己負担の支払総額が、限度額「57,600円」を超えているので、
超えた「3,400円」が払い戻しされる…ような気がしますが、それぞれが別々で計算されるため、ここでは払い戻しはありません。
その他
限度額適用区分「オ」について
限度額適用区分「オ」(住民税非課税世帯)の方は、限度額[35,400円]となるに加えて、入院時の食事療養費(入院時のご飯)が、限度額区分「ア」〜「エ」の方に比べて減額されます(安くなる!)。
限度額区分「オ」 240円(1食あたり)
ちなみに、【 限度額区分「「ア」〜「エ」】の方は、510円(1食あたり)となっています。
「限度額適用認定証」を申請した際、交付される証明書は、「限度額適用兼標準負担減額認定証」という名称に変わります。※手続き方法は変わりません
まとめ
医療費の支払限度額は、法律の改正などにより変更される場合がありますので、医療機関で高額な支払が発生する前には加入先の健康保険組合や市町村の窓口で、最新の情報を確認することが重要です☑️
また、最近はマイナンバーカードと保険証を紐づけていると、限度額認定証を発行しなくて済む場合があるので病院や役場に確認してみるといいですよ!
本日の記事が誰かのお役に立てますように☺️
今回のように皆さんが得する情報を発信しますので、他の投稿もぜひご覧くださいね!
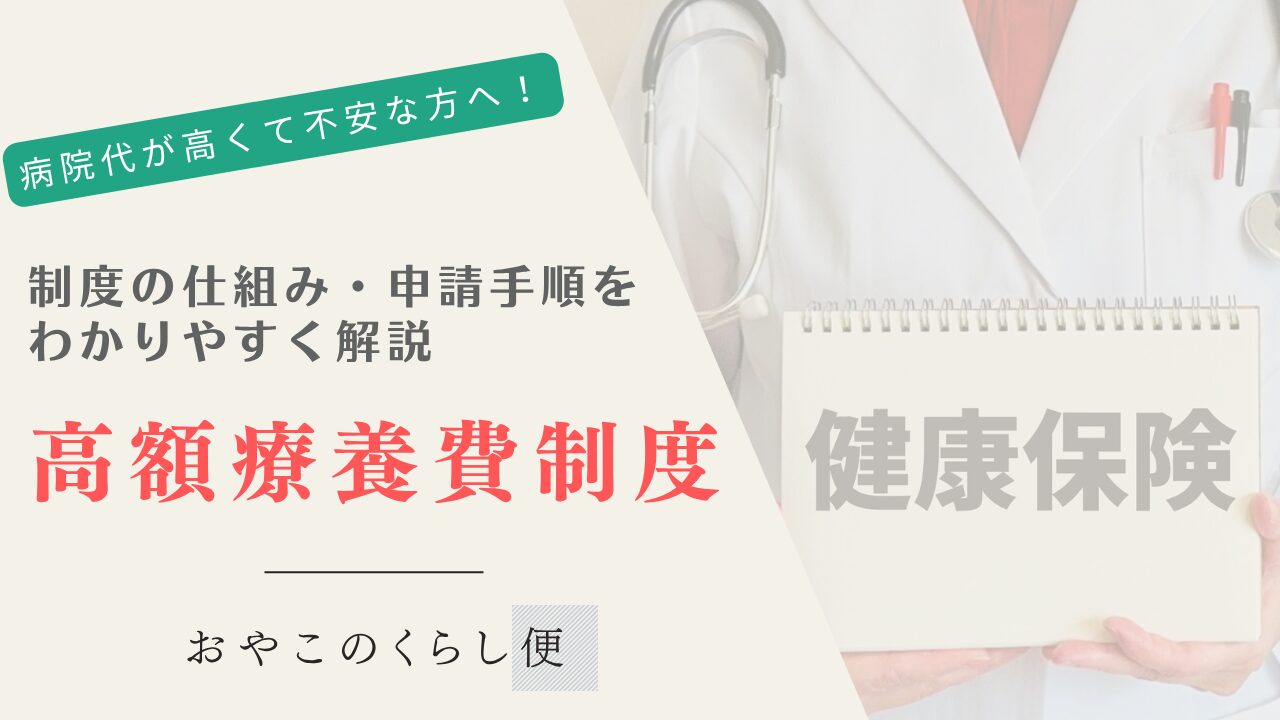


コメント