”療養費”ってパッと聞いてもよくわからないですよね。
”医療費”と何が違うのか。どういったときに申請するのか。実際にいくら支給されるのか。
などわかりやすく解説します!
”療養費”ってなに?
病院などを受診するときに保険証(マイナ保険証や資格確認証を含む)で診療を受けますよね。
通常、保険証を掲示すれば「自己負担3割」で受診(保険診療)できますが、やむを得ない事情で保険診療を受けることができず、自費(10割)で受診したときなど特別な場合には、”本来、健康保険が負担すべき7割分”を療養費として受け取ることができます。
この申請を”療養費の(支給)申請”といいます。

療養費(支給申請)を利用するときはいつ?具体的な事例は?
療養費(支給申請)と言っても、どんなときに利用するかわからないですよね。
主にこんな時に利用できます!(記事へのリンクは下にスクロールしてください!)
- 健康保険の資格取得届の手続き中で、保険診療が受けられなかったとき
(保険証がなくて医療費全額を自己負担した場合) - 急病などやむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき
- 保険証の誤使用による医療費を返還、正しい健康保険に療養費の申請をするとき
- 療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき
- 生血液の輸血を受けたとき
- 柔道整復師等から施術を受けたとき
「1〜6」それぞれの具体的な解説は、リンクからご覧ください✅
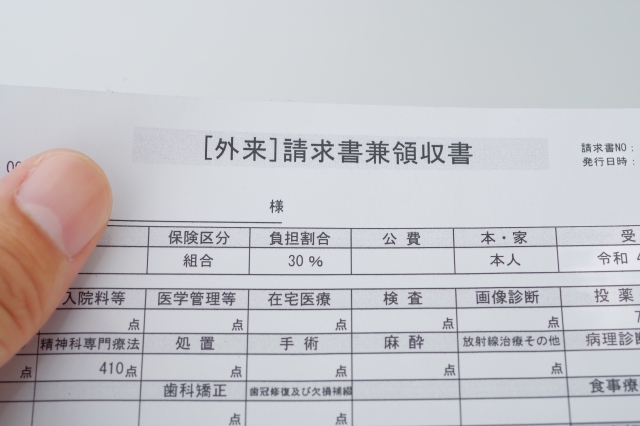
1.健康保険の資格取得届の手続き中で、保険診療が受けられなかったとき
2.急病などやむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき
3.保険証の誤使用による医療費を返還、正しい健康保険に療養費の申請をするとき
情報の公開までお待ちください
4.療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき
情報の公開までお待ちください
5.生血液の輸血を受けたとき
情報の公開までお待ちください
6.柔道整復師等から施術を受けたとき
情報の公開までお待ちください
申請に必要なものは?どこにいけばいい?
上記に解説していますので、各事例ごとにご覧くださいね☝️
申請には期限はあるの?時効は?
”療養費”の申請には期限があります。2年間と覚えておきましょう。
それぞれのパターンによって、時効の起算日(時効のカウントダウンが開始される日)は若干異なりますが、だいたい2年間と覚えておくと良いですね!
| ケース・状況 | 時効の起算日 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ① | 資格取得届の手続き中で、保険診療が受けられなかったとき(保険証がなく、医療費を全額自己負担) | 医療費を支払った日 | 「やむを得ない理由」があることが前提。領収書の保存を忘れずに。 |
| ② | 急病などやむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったとき | 医療費を支払った日 | 緊急性が認められた場合に限る。申請時に説明書類の提出が求められることも。 |
| ③ | 保険証の誤使用により医療費を返還後、正しい健康保険に療養費を申請するとき | 医療費を支払った日 | 誤使用の返還処理後、正しい保険への申請が可能。申請書類に注意。 |
| ④ | 療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセット等を装着したとき | 装具代を支払った日 | 医師の証明書(装着指示書)が必要。対象装具か事前に確認。 |
| ⑤ | 生血液の輸血を受けたとき | 輸血費用を支払った日 | 医療機関からの証明書類(生血輸血証明書等)の提出が必要。 |
| ⑥ | 柔道整復師等から施術を受けたとき | 施術費用を支払った日 | 医師の同意、または症状によっては不要。施術明細と領収書を保管。 |
時効が経過したものはどうなるのか?再申請は可能?
結論!できません…
窓口で受けていたときに、時効を過ぎた申請は、お断りしていましたので、対策方法としては時効の終了日を見据えて早い目に申請をするのが鉄則です。
申請方法は?どこに申請にいけばいいの?
申請の内容や申請先によって申請書の様式はさまざまです。
例を踏まえながら解説しますね!
⚠️お住まいの自治体により申請書の様式は異なりますのでご注意ください。
例)東京都新宿区
🔍検索方法 「東京都新宿区 療養費申請」
HP内に申請書が複数あり、郵送での対応も可能
〈①〜③・⑤〜⑥〉申請書(医科)https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000361868.pdf
〈④〉申請書(治療用装具) https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000361869.pdf
新宿区では治療用装具(弾性ストッキングや義足など)の場合のみ様式を変更しているようです。
私としては、市区町村役場の窓口での申請がスムーズにできるのではないかと感じています。
⚠️加入している健康保険組合によって異なりますので、詳細はHPをチェック!
例)全国健康保険協会
🔍検索方法 「全国健康保険協会(協会けんぽ) 療養費申請」
〈立替払等〉申請書 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/k_tatekae_n2412.pdf
〈治療用装具〉申請書 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/kenkouhokenkyuufu/k_sougu_n2505.pdf
立替払等とは、「全額自己負担(10割)を病院や薬局などで支払い、保険者負担分(7割)を支給(返還)してもらうこと」を指します。
全国健康保険協会(協会けんぽ)以外の健康保険組合の方は、保険証や資格確認書に記載されている健康保険組合の名前を検索してみましょう💡
🔍検索方法 「⚫️⚫️株式会社健康保険組合 療養費申請」
こんな感じで検索してみると⭕️
よくある質問
申請に必要なものは?何を用意すればいい?
各事例ごとに詳しいことは上記で解説しています。
こちらをクリック!
申請したらいくら支給(返還)されるの?
療養費の申請では、保険者負担分(7割)の支給申請になります。
つまり、「全額(10割)支払った医療費 × 0.7」で計算することができます。
例)A病院で「28,000円(全額自己負担)」支払
例の場合、療養費として支給される金額は、28,000円×0.7(7割)=19,600円となります。
なぜ7割分が支給されるの?根拠は?
保険証を掲示して医療機関を受診する場合、3割負担(8,400円)で済みますよね。
残りの7割(19,600円)は、保険者(国保や全国健康保険協会などの健康保険の運営者)が負担してくれているからなんです!
療養費は、保険者(国保や全国健康保険協会などの健康保険の運営者)が本来負担すべき金額(7割)を支給してくれます。
※70歳以上の方で自己負担2割や1割の方もいますが、ここでは現役世代(70歳未満)の一般的な例を用いています。
領収書を無くしたよ…再発行はできる?
できる場合が多いです。
私が勤務していた自治体では、領収書を紛失した人に「領収済証明書」を発行していました。
ただし、自治体や健康保険組合によっては、領収書の再発行ができない・有料の場合がありますので、詳細は電話などでご確認ください。※HPに掲載されていない場合が多いです。
領収書は、確定申告での医療費控除に使用できる場合がありますので、捨てないようにしてください!
また、療養費として”支給”が決定された場合に「支給決定通知書」などの金額がわかる証明書がありますので、こちらも捨てないようにしましょう。
✅ 療養費申請は「期限・書類・申請先」を押さえて早めに行動しよう!
療養費の制度は、通常の保険診療(保険証を掲示して受診など)ができなかったときに自己負担を大きく減らすことができる心強い仕組みです。
ただし、申請には2年間の期限があり、必要書類や申請先もケースによって異なります。
書類不備や期限切れで申請できない事態を防ぐためには、医療費の領収書・証明書類をしっかり保管し、早めに準備することが大切です。
医療費は家計への負担も大きいもの。
療養費申請だけでなく、医療費控除や各種保険制度を組み合わせれば、さらに負担を軽減できます。

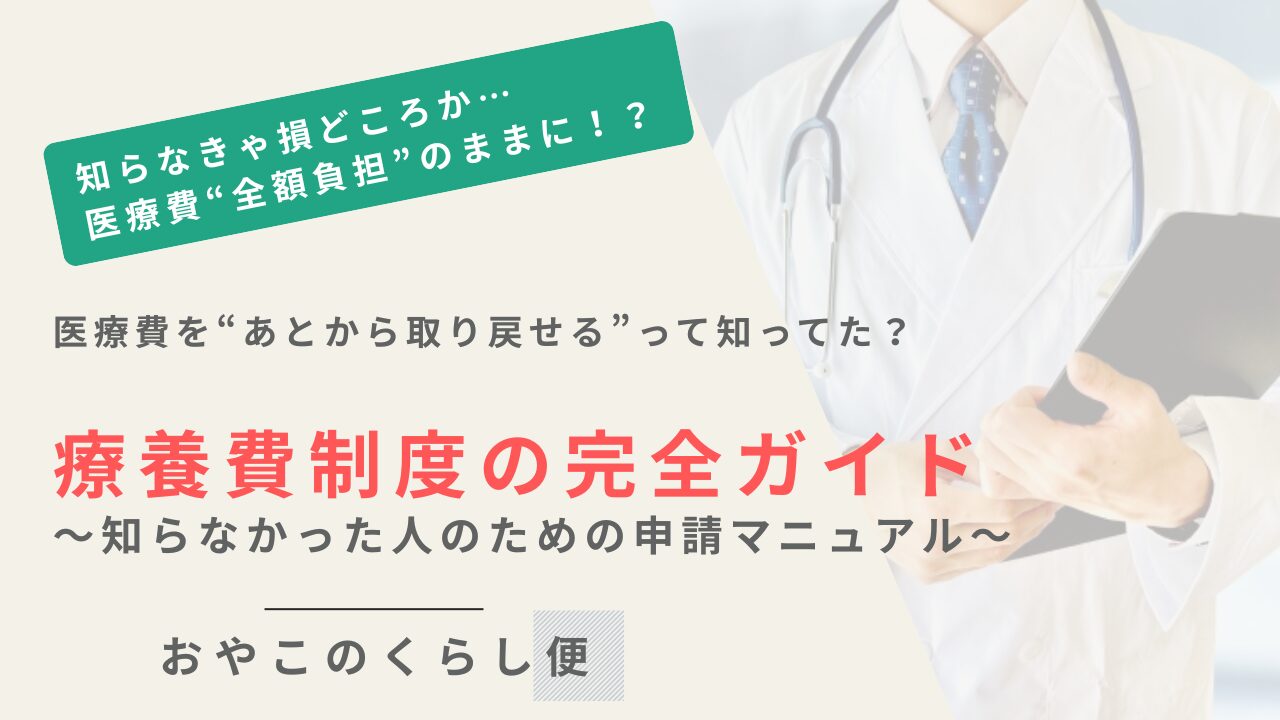




コメント